横浜自然観察の森
2026年1月の観察記録
1月は、植物の実が売り切れになり、さらに人にも慣れてきたためか、道沿いに小鳥が出てくるようになりました。道沿いのウツギの木の実にはウソがつき、イノコヅチやヨモギなどの野草の種にはカワラヒワやシジュウカラなどが、地面にはアオジやシロハラなどが採餌をしていて観察しやすい印象でした。また、1月後半からは、ジョウビタキ、トラツグミの観察頻度が高くなり、草地などの開けた場所でよく見られました。猛禽類は、越冬中のノスリに加え、ミサゴ、トビ、オオタカなどが晴れた空を飛び、関谷見晴台などの眺望が良い所からの観察を楽しませてくれました。
2026年1月に見られた鳥
キジバト、ミサゴ、オオタカ、トビ、ノスリ、コゲラ、アオゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、シメ、ウソ、カワラヒワ、アオジ、クロジ、コジュケイ、ソウシチョウ、ガビチョウ(計26種 調査日:2026年1月24日)
最新の自然情報はブログでも更新していますのでぜひご覧ください。これらの記録の収集には、横浜自然観察の森友の会の皆さんのご協力をいただいています。毎月第2日曜日は友の会主催の探鳥会を行なっています。
横浜自然観察の森トップページ
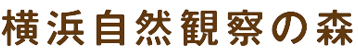
横浜自然観察の森|2025年の記録
横浜自然観察の森トップページ 2025年12月 12月、横浜自然観察の森の落葉樹の葉は落ちきり、比較的に野鳥が見やすい季節を迎えます。道を歩くと、シロハラなどのツグミの仲間が地面の落ち葉をひっくり返す音や、色々な種類の小鳥が群れになって移動して木々に成る実を食べていく風景を楽しめます。観察の森には、野鳥が食べる実が成る木が色々な種類生えており、種類ごとに順番に実をつけていきます。例えば、12月下旬に実が熟していたのは「ツルマサキ」。木に巻き付くツル性の木で、実が熟すと実が裂けて、中からオレンジ色の種子が出てきます。この種子を野鳥が食べます。私が見た時には4羽ほどのメジロと、5羽ほどのウソが集まり、長い時間ツルマサキの周りに留まっていました。メジロは種子を丸飲み、ウソはくちばしで種子を潰しながらどんどん食べていきます。ウソが食べカスをくちばしにつけながらモシャモシャと食べていく様子は典型的な食いしん坊キャラのようです。ただ、ツルマサキ目線で種子散布を考えると、種子を潰されてしまうので喜ばしくないかもしれません。メジロの丸飲みの方が有難いのかなと、考えを巡らせ


